↓タップで応援お願いします!
にほんブログ村
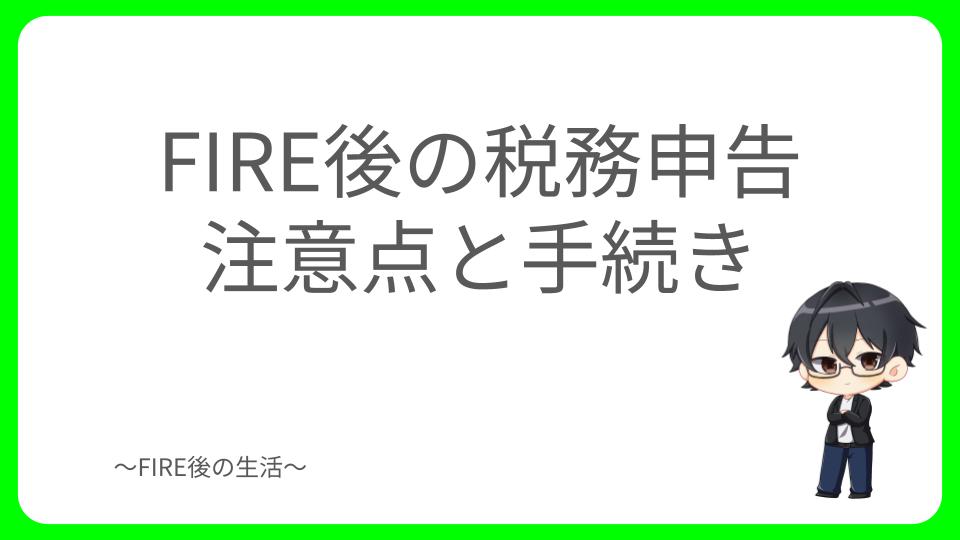
FIRE(Financial Independence, Retire Early)を達成し、早期リタイアを実現した後も、税務申告や各種手続きは避けて通れません。
退職金の課税、住民税の支払い、国民健康保険や年金の手続きなど、FIRE後の生活には多くの税務上の注意点があります。
本記事では、FIRE後に必要な税務申告のポイントと手続きについて詳しく解説します。
退職金は「退職所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
退職所得の計算式は以下の通りです。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように計算されます。
この計算式により、退職金の課税額を把握し、適切な税務申告を行うことが重要です。
退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出する必要があります。
この申告書を提出することで、源泉徴収が適切に行われ、原則として確定申告は不要となります。
提出を忘れると、税率20.42%で源泉徴収され、確定申告が必要になる場合がありますので注意が必要です。
住民税は前年の所得に基づいて課税されます。
そのため、FIREを達成して収入が減少した場合でも、前年の高い所得に基づく住民税の支払いが必要となります。
特に退職金や資産売却益がある場合は、翌年の住民税が高額になる可能性があるため、資金計画を立てておくことが重要です。
退職時期によって、住民税の納付方法が異なります。
例えば、1月1日から4月30日までに退職する場合、退職月から5月までの住民税の未納分が退職金から一括で差し引かれます。
退職日が6月1日から12月31日までの場合は、退職者の意思で、翌年5月までの住民税の納付方法を一括徴収か普通徴収か選択することができます。
退職時期によっては、退職金からまとまった金額の住民税が徴収されることがあります。
退職後は、健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
国民健康保険料は、前年の所得や世帯構成に応じて決定され、市区町村によって差があります。
所得が減少しても、均等割・平等割といった「住民であるだけで発生する保険料」があるため、保険料が高額になる場合があります。
退職後2年間は、これまでの健康保険を任意継続することも可能です。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに決定され、原則2年間変わりません。
国民健康保険と任意継続の保険料を比較し、有利なほうを選択することが重要です。
20歳から60歳未満の方は、退職後も国民年金への加入が義務付けられています。
2025年度の国民年金保険料は月額16,980円で、年間では約20万円の負担となります。
扶養している配偶者がいる場合、配偶者にも国民年金保険料がかかるため、家計への影響を考慮する必要があります。
FIRE後の収入源として、配当所得や不動産所得、資産売却益などが考えられます。
これらの所得は、総合課税または分離課税のいずれかを選択して申告する必要があります。
課税方式の選択によって、税額や住民税、国民健康保険料に影響が出るため、シミュレーションを行い、最適な方法を選択することが重要です。
確定申告は、e-Taxを利用することで、自宅からオンラインで手続きが可能です。
マイナンバーカードを活用することで、源泉徴収票やふるさと納税、医療費控除などのデータを自動で取り込むことができ、申告作業が効率化されます。
FIRE後の生活では、税務申告や各種手続きが重要なポイントとなります。
退職金の課税、住民税の支払い、国民健康保険や年金の手続き、確定申告など、事前に情報を収集し、計画的に対応することが求められます。
適切な手続きを行い、安心してFIRE後の生活を送るために、税務に関する知識を深めておきましょう。